縄文ガーデン
まいぶんKANの縄文ガーデン


エゴマの芽
エゴマはシソ属の植物です。
葉や種(果実)がシソと同様に食用になるので、現代でも栽培されています。
エゴマは春に種をまくと、2週間くらいで芽を出します。
まいぶんKANでは去年のこぼれ種が早く芽を出すので、5月中旬くらいから見ることできます。

穂が出て果実が中に蓄えられてきたエゴマ
9月の初めに白くて小さい花をつけたあと、
穂の中に種(果実)ができます。

完熟したエゴマ
9月終わり頃、黄色く紅葉した葉っぱが落ちると完熟します。
開催ワークショップ
エゴマ収穫体験(H30年は10月中旬開催)
-
-
ヤブツルアズキ
縄文時代にあるような野生のアズキは、ヤブツルアズキといいます。これは一度まいたら毎年生えてきます。5月後半に芽が出て、7月終わりから8月にかけて開花します。収穫はサヤが真っ黒になってから。つまむとパチン!とはじけてしまうので、注意して採集します。
関連ワークショップ
縄文の植物を収穫してみよう(H30年は10月開催)
-
-
アサツキ
ヒガンバナ科ネギ属の球根性多年草。
花は5月頃に咲きます。
-
-
カラムシ
カラムシは繊維をとることができる植物です。初夏の青々とした茎を刈り、外皮をはぐと美しい白~緑の繊維を取り出すことが出来ます。刈ってもまた伸びるので、シーズンに2回~3回繊維をとることができます。
関連ワークショップ
カラムシで腕輪をつくってみよう(H29年8月中旬に開催)
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町埋蔵文化財保存活用施設 まいぶんKAN
〒939-0723 富山県下新川郡朝日町不動堂214
電話番号:0765-83-0118
ファックス:0765-83-0118








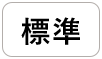



更新日:2024年11月27日