柳田遺跡
柳田遺跡
柳田遺跡(中心時期は縄文時代前期後葉)
柳田遺跡は前期後半を中心に縄文時代後期まで長く続いた遺跡です。
玦状耳飾や石器類、石斧などが多数出土し、加工具も豊富であることから、石器作りのムラと考えられます。

柳田遺跡縄文土器深鉢(前期後葉)
縄文土器深鉢 (福浦上層式期)

筋砥石
玉や石器を磨いた砂岩製の砥石です。

玦状耳飾(けつじょうみみかざり)
蛇紋岩、透閃石岩、滑石などで作られた玦状耳飾が多数見つかっています。
製作に使われた砥石などの道具類の出土が多いことから、石器製作の工房だったと考えられます。

-
ヒスイ製敲石
ヒスイは玉(装身具)の材料として知られていますが、日本で最初にヒスイが使われたのは、ハンマー(敲石)としてでした。
ヒスイはとても硬く、比重が重くずっしりとして、割れにくい性質があります。また、海岸で拾えるヒスイは波に磨かれても扁平になりにくいので、握って敲くのに適した形だったのでしょう。

-
玦状耳飾の未成品
平たい石の中央を砥石で擦り切り、ミゾをつけています。石材には蛇紋岩(じゃもんがん)や透閃石岩(とうせんせきがん)、滑石(かっせき)を利用しています。
-
平砥石
砥石は玉を磨くほか、磨製石斧などを磨く場合にも使います。
柳田遺跡からは磨製石斧も多く出土しています。
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町埋蔵文化財保存活用施設 まいぶんKAN
〒939-0723 富山県下新川郡朝日町不動堂214
電話番号:0765-83-0118
ファックス:0765-83-0118








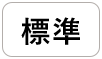



更新日:2024年11月27日