境一里塚
境一里塚(さかいいちりづか)
県・史跡 昭和40年1月1日指定
住所
富山県下新川郡朝日町境字東地1873-1

県境の境川にかかる国道8号戦境橋の西方海側に、榎等が繁る高さ約3メートルの小さな塚がある。
慶長9年(1604)徳川幕府の命により、江戸日本橋を起点に、東海道・北陸道などの主要5 街道には、1里(36町、約4000メートル)ごとに、里程標の役割を果たす1里塚が築かれた。
境の塚は、加賀藩領東端の1里塚で、街道をはさみ、南北を一対にして、5間(約9メートル)四方の規模に盛土して、榎が植えられていた。ここを通る旅人は、その木陰で憩い、歩いた道のりを計り、旅程の目安にしたのである。

南側の塚は、明治以降の国道の拡張改新のためにとり壊され、昔の様子をとどめるのは、北塚だけである。県内でもほとんどその姿を消し、今では江戸時代の陸上交通の状況を語る遺跡としては、大変貴重なものとなった。
このため、昭和54年(1979)の国道改良工事の際にも、残されたこの北塚の周辺を整備し、往時の面影を取り戻すよう努力が払われた。
横水(よこみず)・一里塚
町・史跡 昭和42年12月5日指定
住所
富山県下新川郡朝日町横水123

三日市から泊までの北陸道は、古くから、扇状地を横断して、入善を経由する直進路の下往来が使われていた。しかし、ここは黒部川の氾濫原で、黒部四十八ヶ瀬と呼ばれて川筋が多く、洪水や増水時には、通行を拒むことが多かった。寛文二年加賀藩主前田綱紀の命により、扇状地を南に迂回するように、扇頂の愛本峡に橋がかけられた。ついで舟見、浦山が宿駅に指定されて、上往来が整備されると、かなり遠回りにはなるが、安全のため、参勤交代コースともなり、利用する旅人もしだいに多くなった。従ってそのころ、上往来にも、北陸道の例にならい、一里ごとに、街道の里程標となる一里塚が築かれ、その一対が、この横水にも置かれたものと考えられる。
この塚は、黒部川扇状地の陸上交通の変革をしるためには、まことに貴重なものである。
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109








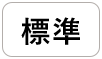
更新日:2023年03月31日