住宅用火災警報器の設置
全家庭に住宅用火災警報器の設置が義務化されました!
消防法及び火災予防条例の改正が行われ、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
1.なぜ義務化されたのか
住宅火災における死者数(放火自殺者を除く。)は、平成15年・16年と2年連続して1,000人を超え、建物火災における死者の約9割に及び、住宅火災による死者の約7割が「逃げ遅れ」によるものです。
また、死者の半数以上が高齢者であり、今後高齢化の進展とともに増加するおそれがあります。
以上のことから、平成16年6月に消防法が改正され、火災を早期に発見し逃げ遅れを防ぐこと等を目的として、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けとなりました。
2.設置義務化の時期は
- 新築住宅については、平成18年6月1日から
- 既存の住宅については、平成20年5月31日までに住宅用火災警報器の設置が必要です。
(既存住宅とは、平成18年6月1日に現に存ずる住宅又は新築、増築、改築等の工事中の住宅をいいます。)
3.義務化される建物は
一戸建て住宅、共同住宅、アパート、社宅、併用住宅等の住宅部分(店舗併用住宅、事務所併用住宅など)
(スプリンクラー設置や自動火災報知設備が取り付けられている場合は、設置する必要がありません。)
4.住宅用火災警報器とは
火災時の煙や熱などを自動的に感知し、警報音や音声で火災を知らせる機器です。
(1)感知器で分類すると
- 煙感知器=煙が火災警報器に入ると警報音を発する。
(住宅部分の寝室、階段及び廊下などに適する。) - 熱感知器=火災警報器の周囲温度が一定の温度(約60度~65度で感知)に達すると警報音を発する。
(調理などで煙や水蒸気が発生する台所などに適する。)
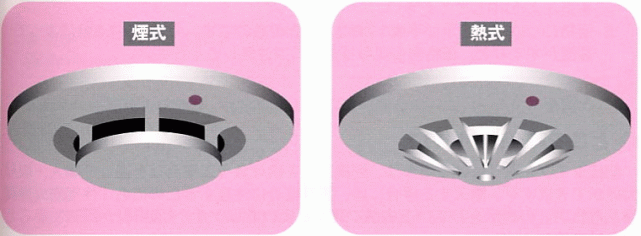
義務化されたのは、煙感知器です。寝室、階段、廊下等には煙感知器を付けて下さい。
なお、義務はありませんが台所には熱感知器を設置されると、より安全で安心です。
(2)電源で分類すると
電池式(10年寿命のものもあります。)と家庭用電源(AC100V)を使うものがあります。
(3)取り付ける位置で分類すると
「壁用」、「壁・天井用」、「天井用」タイプがあります。
住宅用火災警報器は、電気店やホームセンターなどで購入できます。(消防署では販売することはありません。)価格は5千円から1万3千円程度です。
5.どこに設置するのか
必ず設置
- 寝室=普段就寝している部屋に設置します。
- 階段=寝室がある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。ただし、避難階(1階など容易に屋外に避難できる階)は除きます。
条件により設置
- 階段(3階建て以上の場合)
(1)寝室が3階以上にある場合、寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外階段を除く。)の踊り場の天井又は壁に設置します。
(当該階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要。)
(2)寝室が避難階(1階など容易に屋外に避難できる階。)にのみある場合は、居室のある最上階の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
- 廊下=火災報知器を設置する必要がなかった階で、床面積7平方メートル(4畳半)以上の居室が5つ以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。
6.感知器の取り付け位置は
感知器は自分で取り付けることができます。
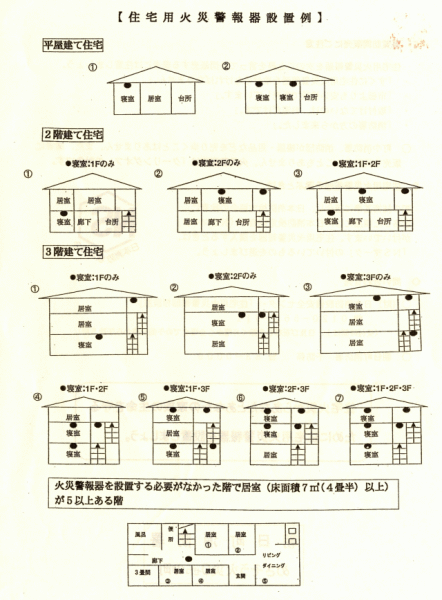
7.悪質訪問販売にご注意
住宅用火災警報器を、次のこと等を言って訪問販売する業者には注意しましょう。
- 「すぐに住宅用火災警報器を取り付けなければなりません。」
- 「市価よりも安い値段で販売しています。」
- 「取り付けてないのは、お宅だけです。」
- 「消防署のほうから来ました。」
町や消防署、消防団が機器・用品などを売り歩くことはありません。また、業者に販売を委託することもありません。 火災警報器は「クーリングオフ」の対象です。
8.住宅用火災警報器を選ぶときは
国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した製品には、日本消防検定協会の「NSマーク」が付いています。住宅用火災警報器を購入するときは、「NSマーク」の付いているものを選びましょう。

問い合わせ先
財団法人日本消防設備安全センター「住宅用火災警報器相談室」
新川地域消防組合朝日消防署
- 電話 0120-565-911
- (受付時間は土曜日、日曜日及び祝祭日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時)
- 電話 0765-83-0009
- 住宅火災からあなたとあなたの家族の生命を守るために住宅用火災警報器を設置しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0731 下新川郡朝日町道下1062
電話番号:0765-83-0009
ファックス:0765-83-1867








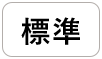
更新日:2023年03月28日